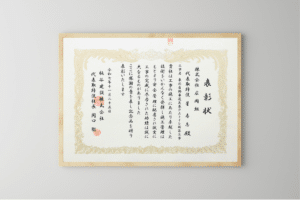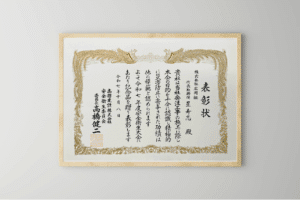「TAUE」挑戦第2弾として、先日、インドネシアから来ている技能実習生たちと、稲作りの大切な工程である「中ぼし」と「溝切り」そして「畦の草刈り」作業に取り組みました。
慣れない日本の農業作業ですが、彼らは真剣な眼差しで、一つひとつの作業を丁寧に行ってくれました。
目次
Toggle稲の健康を育む「中ぼし」と「溝切り」
まずは、稲作りに欠かせない「中ぼし」と「溝切り」について簡単にご紹介します。
中ぼし(なかぼし)とは?

「中ぼし」は、田植え後、稲の茎が増え始める時期に、一時的に田んぼの水を完全に抜いて土を乾かす作業のことです。
なぜ行うの? この作業を行うことで、稲は土の中にしっかりと根を張り、無駄な茎の増殖(分げつ)を抑えることができます。まるで稲に「もうこれ以上は増やさなくていいよ、その代わりもっと根を張って強くなりなさい!」とメッセージを送るようなもの。これにより、丈夫で倒れにくい稲に育ち、栄養が実に集中して美味しいお米が育ちます。土の中の有害なガスを抜き、土壌環境を良くする効果もあります。
溝切り(みぞきり)とは?

「溝切り」は、田んぼの中に水が流れやすいように溝を掘る作業です。
なぜ行うの? この溝があることで、中ぼしで水を抜く際に田んぼ全体の水が均等に抜け、土がムラなく乾きます。また、長雨などで田んぼに水が溜まりすぎた時も、この溝が排水路の役割を果たし、稲が水に浸かりすぎて弱ってしまうのを防ぎます。中ぼしの効果を最大限に引き出し、稲が健やかに育つための重要なサポート役なんです。
実習生たちの奮闘!気づけば溝切り競争に‼
実習生たちは、中ぼしのために水を抜いた田んぼに入り、泥に足を取られながらも慣れない道具を使って丁寧に溝を切っていきました。最初は戸惑いも見られましたが慣れてくると、裸足でどんどん田んぼへ。泥んこの感触も全然平気みたいで、むしろ楽しんでるように見えました。作業中にヘビが出てきても全然怖がらず素手でサッと捕まえて興味津々で観察。これぞインドネシアの大自然で育った彼らならですね。溝切りの作業では、いつの間にか「誰が一番早く、きれいにできるか勝負だ!」という感じで、もう作業というよりゲーム感覚。大変な農作業も、彼らにとってはワイワイ楽しむ時間に見えました。


そして、もう一つ重要な作業が畦の草刈りです。
田んぼの縁を美しく保つ「畦(あぜ)の草刈り」

「畦(あぜ)」とは、田んぼと田んぼの境や、田んぼと畑・道路などの境にある土を盛った部分のことです。
なぜ草刈りをするの? 畦に生い茂る草は、見た目が悪いだけでなく、稲に届くはずの養分を奪ったり、病害虫の隠れ家になったりすることがあります。また、雑草の種子が田んぼの中に落ちて、稲の生育を邪魔することも。そのため、定期的に草刈りを行い、清潔で管理しやすい状態を保つことが大切です。
実習生たちは、草刈り機を器用に操り、きれいに畦を刈り取ってくれました。慣れない機械の扱いや30度超えの暑さの中での作業でしたが、額に汗を流しながらも、黙々と作業を続ける姿は本当に頼もしかったです。


作業後のご褒美と、初めての「納豆巻き」体験!

すべての作業を終えた後は、社長宅でみんなでお昼ご飯をいただきました。汗を流した後の食事は格別で、みんなで和気あいあいと楽しい時間を過ごしました。
その中で、実習生たちが初めて口にしたのが「納豆巻き」でした。独特の匂いと粘り気に、最初は少し困惑した様子でしたが、恐る恐る一口食べると、その表情は驚きと面白さでいっぱいでした。「これは…不思議な味ですね!」と、彼らにとっては忘れられない体験になったようです。

【TAUE】挑戦!第2弾を終えて
今回の作業を通じて、実習生たちは日本の稲作りの奥深さに触れるとともに、農業作業の難しさや、やりがいを感じてくれたことと思います。そして、日本の食文化にも触れることができ、彼らの頑張りが、秋に出来る美味しいお米へとつながるはずです。
これからも、広岡組では実習生たちと日本の伝統文化である【TAUE】を通じて、共に学び合っていきたいと思います。